

漫画アプリ市場って日本が市場の77%を占めてるって知ってますか?
「漫画アプリって、欲求扇動する天才的なアイデアですよね」
こんにちは、Dです。
今回は、現代人の時間泥棒の代表格、
「漫画アプリ」
のビジネスモデルから、情報発信の極意を学ぶ
ということについてお話しします。
「え?Dさんが漫画?」
って意外ですか?笑
私、アニメも見ますし、
アニメに関するブログも裏でいろいろ書いてたりもします笑
漫画やアニメって、
実は情報発信ビジネスについて
学べることがめちゃくちゃ多いので、
そのへんを私がどう見ているのか?
と思い、アウトプットも兼ねて
ブログにしています。
今回は漫画アプリから学ぶ情報発信。
についてです。
皆さん、漫画アプリ使ってますか?
私は結構どっぷりとハマっております。
トイレの中、寝る前のひととき…
気づけばスマホ片手に漫画の世界へダイブしています。
そして、恐ろしいことに、
気づけば課金している自分もいます笑
「いやいや、この先は気になるけど、課金はしないぞ」
と固く誓ったはずなのに…。
なぜ、私たちはこうも簡単に漫画アプリの策略にハマってしまうのか?
その答えは、
漫画アプリのビジネスモデルが、
人の「欲求」を巧みに操るプロだからだと気づきました。
「天才やん」
とさえ思ってしまいましたね。
しかもこのビジネスモデル、
情報発信にも使えるな、というか使ってるなと。
このようにですね、
日本における漫画アプリの盛り上がりについては、
単なるマーケティングの巧さだけでは説明がつきません。
これはもはや、
日本人の特性を捉えた
「国民欲求扇動マシーン」と呼ぶべきシロモノです。
今回のブログでは、
そんな漫画アプリのビジネスモデルから紐解く
情報発信のヒントと言いますか、
私の思うところ、
というのを
お届けします。
先日
ふと、
漫画アプリってめっちゃ儲かってそうよな。
って妻との会話してからというもの、
ちょっと言語化してみるか、
と始まった今回の内容。
こうやって、
気になったことを放置せず
情報を消化し
置き去りにすることなく
期限内にやり切る。
というのを、
2025年はテーマにもしています。
ということで、
日本の漫画市場がなぜこれほどまでに巨大なのか、
その文化的、心理的、さらには進化論的背景まで深掘りしていきます。
23時間の焦らしプレイ
漫画アプリのビジネスモデルの根幹、
それは「待てば無料」という一見慈悲深いシステムではないでしょうか。
私も2つのアプリを使っていますが、
どちらも、「待てば無料」
というプレイが基本です。
ですが、
たまに
「え、焦らしなしのいきなりやつ?」
(すみません、一才、下系ではありませんのであえて言わせていただきますね)
というのもありますが、
「23時間待てば次の話が無料で読める」
という甘い囁き。
しかし、
この「待てば無料」こそが巧妙な罠。
「え、待たれへん…www」
これは私じだけじゃないはず。
むしろ、一気見したくて
うぉおおおおおおおっ!!!
って課金したことある方がほとんどかと思います。
「え?だって待てないでしょw??」
考えてみてください。
私たちは、23時間という長い時間を
「待つ」
という行為に費やすことになります。
その間、頭の中では
「次は何が起こるんだろう?」
「あのキャラクターはどうなるんだろう?」
という期待と妄想が膨らみ続けます。
むしろ、読み終わって速攻気になったりします…
そして、
ついに23時間が経過し、無料で読めるようになった瞬間、
私たちはその「報酬」に飛びつきます。
これはまさに、
「虚無の時間を至福の時間に変える極上のエンタメ」
ですよね。
本来、何も生み出さないはずの
「待つ」
という時間を、
漫画への期待値を高めるための
「仕込み時間」
へと変えてしまうのですから。
たかがマンガ、されど漫画。
こうやってマインドシェアとってきてるんですね。
さらに、
日本人は農耕民族的な性質から、
この「待つ」という行為、
つまり
「長期的な物語」
を楽しむ素養が強く、
西洋の狩猟民族的な「瞬間的な刺激」を求める性質と比べても、
日本人の待つ、忍耐とも言いますか、
そういった面も、世界的に見ても強いのではないか、とも言えますね。
実際に調べてみたところ、
日本人は待つことに対して
独特な特徴を持っているということがわかりました。
日本人は
「行列に並んで待つことに抵抗感がある」
という回答が57.2%と、
アジア6カ国の中では最も高い数値を示しています。
しかし、面白いことに、
実際の「待てる時間」というのは、
日本人が最も長いという矛盾が見られました。
- 人気レストランで31.6分
- 遊園地のアトラクションで48.5分
- テイクアウトで19.7分
これらはいずれも調査対象国の中で最長となっていました。
日本人の特徴として、
「意識と行動のギャップ」が存在します。
待つことに抵抗を感じながらも、
実際には長時間待つことができる。
さらには進んで行列に並ぶ傾向もある。
これは日本特有の
「空気を読む」文化
とも関連している可能性がありますね。
このように、日本人には待つ文化、
というのも根付いているわけです。
これが、週刊連載のジャンプ文化や、
長期連載の漫画が隆盛を極める一因ともなっているのではないでしょうか。
まさに、日本人の特性を利用したビジネスモデル。
ですよね。
そして、23時間という時間設定は、
日本人の特性を計算し尽くした「焦らしプレイ」です。
24時間じゃなく、23時間。
というのがミソですね。
情報発信においても、
この「仕込み時間」の概念は非常に重要かと思います。
期間限定とか、何日後、とか、
欲求を刺激する手法ですよね。
・希少性による購買意欲の刺激
・話題性の演出
・コラボ
・バイラル効果
など。
読者が、あなたの次の発信を待ち望むような状況を作り出すことができれば、あなたの発信は読者にとって「報酬」となり、その価値は飛躍的に高まるかと思います。
例えば、
ブログで連載形式の記事を書く場合、
各記事の最後に「次回は〇〇について解説します!
と予告を入れることで、読者の期待値を高め、
次の記事への興味を喚起することができます。
セールスしてコンテンツに流したり、
活用方法はいろいろありますよね。
「限定」の魔力、特別感が心を惑わす。希少性の極意
「期間限定無料」
「今だけポイント増量」
など、
漫画アプリは「限定」という言葉を巧みに使い、
ユーザーの購買意欲を刺激してきます。
他にもコインが当たるガチャとかもありますよね。
あれはタイムシェア作戦です。(ポイ活も同じですね。)
漫画アプリだけじゃなく、「限定」という言葉は、よくありますよね。
なぜか人の心をザワつかせる魔力とも言いますか。
「今を逃したら損をするかもしれない」
という焦燥感を煽り、行動を促すあれです。
この限定、というのは、特別感で心を操る心理テクニックです。
「あなただけに特別なオファーです」
と言われたら、誰だって悪い気はしませんよね。
漫画アプリは、
この「特別感」を演出することで、ユーザーの心を巧みに操り、
課金へと誘導しているのです。
情報発信においても、
「限定」の魔力と「特別感」
というのは超絶有効です。
「先着10名様限定」
「期間限定特典」
「今回の企画参加者限定」
など、「限定」という言葉を使うことで、
読者の行動を促すことができます。
ただし、「限定」の乱用は逆効果です。
「限定って言ってるけど、いつもやってるやん!」
と読者に思われてしまうと、
信頼を失うことになりかねません。
「限定」を使う際は、本当に
「限定」であることを明確にし、
読者に
「特別感」
を感じてもらえるように工夫できれば
セールスは意外にも簡単だったりもします。
「習慣化」の牢獄へようこそ。日常への侵食…
漫画アプリの多くは、
毎日ログインすることでボーナスポイントがもらえるなどの特典が用意されていますね。
これは、
ユーザーにアプリを開くことを習慣化させ、
アプリへの接触頻度を高めるための戦略です。
まさに『習慣化』の牢獄へようこそされてまんまと策略にハマってしまうあれです。
決して悪く言っているわけではありません。
むしろ、褒めちぎっていますw
この習慣というのは、恐ろしい威力を発揮します。
これは、情報発信や漫画アプリだけでなく、読書、勉強、筋トレ、何にでも応用できます。
今回の漫画アプリで言えば、
無意識のうちにアプリを開き、
漫画を読み、そして課金してしまうのです。
恐ろしいまでの戦略です。
情報発信においても、
読者に「習慣化」してもらうことは非常に重要です。
例えば、毎日決まった時間にブログを更新したり、
毎週決まった曜日にメルマガを配信したりすることで、
読者の生活の中にあなたの発信を組み込むことができます。
「〇曜日には〇〇さんのブログを読むのが楽しみ」
と読者に思ってもらえれば、あなたの発信は読者の生活の一部となり、その価値は飛躍的に高まります。
ただし、「習慣化」の牢獄に閉じ込められた読者が、
あなたの発信に飽きてしまわないように、常に新鮮で魅力的な情報を提供し続けることが重要です。
(私はまだ毎日というのが厳しいですが、毎週決まった曜日、時間したいな、とは考えています)
日本の漫画市場を巨大化させた深層心理
なぜ、日本ではこれほどまでに
漫画アプリが普及しているのでしょうか?
その理由は、
単なる経済的・技術的な要因だけではない、
と思い、
日本人の心理的・文化的特性、歴史なども関係しているのでは?
と思い少し調べてみました。
日本人の特性と漫画文化
日本では、漫画は単なる娯楽ではなく、文化そのものです。
そして、日本人は「物語を重視する国民性」を持っています。
情報発信でも、ストーリーが最強、とも言われていますね。
古事記、源氏物語、歌舞伎、浮世絵など、
日本の伝統文化はストーリーを重視し、それが漫画文化へと発展しています。
いつの時代も、
物語を通じて共感や学びを得る習慣が根付いているんですね。
進化論的観点:物語は人類の生存戦略
進化論って、
実は情報発信でもよく使われたりするんですけど、
聞いたことないですかね?
人類というのは、
言語を獲得する前から物語(神話や絵)で情報共有していましたんですね。
進化の過程で、
ストーリーを理解できる能力が生存に有利だったとされています。
日本人はこの物語文化を、極端に発展させた民族とも言えます。
そして日本人は
「空気を読む」
「他者の感情を察する」
能力が高い。
いわゆる「ハイコンテクスト文化」というのを形成しています。
漫画は絵とセリフで感情をダイレクトに伝えられるため、
日本人の高い共感能力と非常に相性が良いとされています。
神話的視点:アニミズムとキャラクター文化
日本は神道(アニミズム)の影響が強いともされています。
「すべてのものに魂が宿る」
という価値観も持っています。
これが、キャラクターに感情移入しやすい文化、
へとつながっていたりします。
例えば、ドラえもんやピカチュウ。
人間以外(ロボットや動物)にも人格が与えられますよね。
さらに、日本の神話では、
西洋の「善vs悪」の二元論とは異なり、
「主人公が試練を乗り越え成長する」
王道のストーリーが多く見られます。
(桃太郎、浦島太郎など)。
これが、現代では少年漫画の成長ストーリー
(ワンピース、ナルトなど)に繋がっています。
おもしろいですよね。
これだけ色んなものが繋がるって。
神話とか、進化論とか、
情報発信始めるまで全く興味すらなかったんですが、
今では、調べては話してと、
人って、ということを知るのが楽しくなっています。
この、無知を知ることを知る、という言葉を残した
古代ギリシャ人の、ソクラテスっていう人、ご存知ですか?
「我は何も知らないことを知る」(”I know that I know nothing”)
これが、哲学者ソクラテスの言葉です。
この言葉は、
「無知の知」
として広く知られ、
自分が知らないことを自覚していることの重要性を説いています。
つまり、
「自分には知らないことがあることを自覚している」
という意味を持っています。
ソクラテスはこの考えを通じて、
「真の知恵とは自分の無知を認識することから始まる」
と説いています。
最後に:日本人は「漫画を愛する」よう最適化されていた…
漫画アプリのビジネスモデルは、
人間の「欲求」を巧みに操る手法です。
まさにそこから巨大な利益を生み出しています。
これ考えた人天才ですね…
この戦略は、
情報発信においてもめちゃくちゃ参考になります。
「虚無の時間を至福の時間に変える極上のエンタメ」
「『限定』の魔力、特別感で心を操る」
「『習慣化』の牢獄、毎日のルーティンに組み込む」
など、
漫画アプリのビジネスモデルから学べる
情報発信のヒントは数多くありました。
そして、
日本の漫画アプリ市場がこれほどまでに巨大なのは、
単なる流行ではなく、長い歴史の積み重ねによるものです。
これらのヒントを参考に、
読者の「欲求」を理解し、それを満たすような情報発信に活かす。
結局のところ、ブランディングさえできたら、
ファンは自動的に増え、ビジネスになっていくんだな、と思います。
今回はここまでです。
ありがとうございました。
次は、哲学者、ブッタの話でおもしろい話があるので、
ユーモアや既視感のない言葉遊びが興味をそそる。
というテーマで書いていこうと思います。
では。

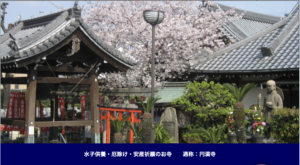
コメント